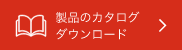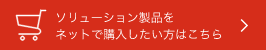[鍵・錠ものがたりー鍵・錠をめぐる歴史ばなし]第2話 鍵のトラブルは1000年を超える?-古代・中世文学と鍵
鍵・錠ものがたりー鍵・錠をめぐる歴史ばなし
遠い昔より、人類と「鍵」は深い関係にあった。そのルーツは現代にも受け継がれている。
今回は古代・中世日本で生まれた文学に遺る鍵・錠の姿を紹介。

「教え如くして旦時(あした)に見れば、針著けし麻(そ)は、戸の鉤穴よりひき通りて出でて、ただ遺れる麻は三勾のみなりき。」
『古事記』(712年編纂)
日本最古の記録文学であり、鍵・錠前が文献上初めて登場するのがこの『古事記』だ。
エジプト、ギリシア、あるいは中国などで使われていた鍵が形状や仕様を変えつつ、海をわたり日本に流入されたのは奈良時代に入ってからと言われている。それ以前は現在でも神社でよく目にする「しめ縄」を張ることで、締まりや結界の存在を他人に知らしめるのみに留められていた。
古事記「上巻」では、天の岩戸伝説をベースにその足跡を伺う事ができる。
速須佐之男命(はやすさのおのみこと)の乱暴に耐えかね天照大御神(あまてらすおおみかみ)が天の岩戸にお隠れになったため、世の中が真っ暗になってしまった。
神々は相談して天宇受売命(あまのうずめのみこと)に命じて、歌と踊りを岩戸の前で行わせた。あまりの賑やかさに、天照大御神が何事かと顔を出したところ、力自慢の天手力男神(あめのたぢからおのみこと)が手を取って引き出し、布力玉命(ふとだまのみこと)がすかさずしめ縄を大神の後方に張り巡らして戻れないようにした場面がある。このしめ縄の先はたとえ神でも立ち入ることは許されない領域(聖地)となるだろう。つまりしめ縄は領域を守る結界の役割を果たしていたとも考えられることから、この記述は日本における鍵・錠をはじめとした物理セキュリティのはじまりといえる。
また「中巻」の崇神天皇の項にある三輪山伝説のもととなる記述がある。
「教え如くして旦時(あした)に見れば、針著けし麻(そ)は、戸の鉤穴よりひき通りて出でて、ただ遺れる麻は三勾のみなりき。」
これは戸に取り付けられた戸締りの装置があり、戸の外から鉤を用いて操作していた描写である。この「鉤」(かぎ)というのは途中で直角にまがったL字状の棒。戸の外から戸に穿った穴を通して落とし締まりを引き上げる仕組みとなっており、ギリシアの神殿錠と同様の仕組みである。

『古事記』から数年後に編纂された『日本書紀』においては、天から落ちてきた2本の鍵が夫婦を大金持ちにさせた、というエピソードがある。
『日本書紀』は文中にハッキリとした鍵の描写がある最初の文献・文学でもある。『古事記』『日本書紀』が編纂される20年前には各官庁や各地域に派遣される役人に城や倉庫の鍵の管理を任せる法令が定められていた。
つまりこの時代には、限られたコミュニティの内とはいえ、鍵が道具として認識され、実生活に活用されていた、ということでもある。
第1話でも鍵が「富・権力」の象徴であったと紹介したが、『日本書紀』から数世紀を経て編纂された『今昔物語』(1120年代以降編纂)では、まさに「権力」の象徴であった鍵を取ることで内外に勝利を示した平将門、その将門に命乞いのためか鍵を渡してしまう役人の描写がある。
「門立てて戸も刺したるにいづくゆか 妹が入り来て夢に見えつる」
「門立てて戸も刺したる盗人の掘れる穴より入りて見えけむ」
安房(現在の千葉県)に珠名という美しい娘がいた。
この娘の美しさは、通行人ですら声をかけられてもいないのに近づいてしまい、隣家の主人は自分の妻に離婚を宣言する前に、彼女に鍵を贈るほどの美しさと愛嬌があったという。
「門立てて戸も刺したるにいづくゆか 妹が入り来て夢に見えつる」
(門を閉じ戸にも鍵をかけたのに、夢の中に現れて来るとは、あなたは一体どこから入ってきたのですか)「門立てて戸も刺したる盗人の掘れる穴より入りて見えけむ」
(門を閉じ戸にも鍵を掛けてありましたが、泥棒の堀った穴から入って現れたのでしょう)
返歌の中にある「盗人の掘れる穴」というのは、建物の外から床下までトンネルを掘り、そこから家屋に侵入する、いわゆる「土蔵破り」に使われる方法である。この犯罪の手法はのちの時代でも行われた。戸締まりをしてもなお、それをくぐり抜け夢枕に立つほどの美女と、障壁をかいくぐりやってくる盗人を重ねる表現方法の豊かさが伺える。
ところで、第1話にて「鍵は家政権の象徴」という話をしたが、おそらく中国から海を経て渡ったものなのだろう。日本にもかつて求婚行為として「鍵を贈る」(家の家政を任せたいという意思表示)という風習があった。

「御門守(みかどもり)寒げなる気配、うすすき出で来て、とみに明けやらず、ごほごほと引きて、錠のいといたく錆びにければ開かずと愁ふるを哀れと聞しめす」
『源氏物語』(11世紀初期成立)
来年の大河ドラマでも注目を集めるであろう『源氏物語』にも鍵・錠をめぐるエピソードが遺されている。「朝顔の巻」にはこのような話がある。
「御門守(みかどもり)寒げなる気配、うすすき出で来て、とみに明けやらず、ごほごほと引きて、錠のいといたく錆びにければ開かずと愁ふるを哀れと聞しめす」
(門番は寒そうな様子で急いで来たが、すぐに戸を開けることができない。ガタガタと戸を引っ張り、「錠前がすごく錆びているから中々開かないのです」と愚痴をこぼしている様子が可愛そうに思われた)
錠前が錆びても、交換も修理もない中使い続ける宮家の状況を嘆く源氏の君(光源氏)のワンシーンである。この後、御門守(門番)が頑張り、どうにか源氏の君は邸内に入る事ができた。
実はこの後の章に「夕顔の巻」というものがある。こちらにおいても、
「かぎを置きまどわして待て。いと不憫なるわざなりや」
(かぎをどこに置いたかわからなくなり、本当に困ったことになりました)
という、源氏の君の乳兄弟、惟光朝臣の台詞がある。
1000年を超える昔、鍵や錠前の形や目的は異なっても、こうした「錆び」や「紛失」のトラブルは変わらず存在していたのだ。