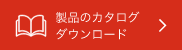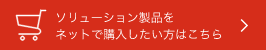[鍵・錠ものがたりー鍵・錠をめぐる歴史ばなし]第7話 新たな鍵を日本から―近代日本カギ開発
鍵・錠ものがたりー鍵・錠をめぐる歴史ばなし
遠い昔より、人類と「鍵」は深い関係にあった。そのルーツは現代にも受け継がれている。
今回は西洋文化の流入とともに変化していった近現代の日本の鍵事情をご紹介。

江戸末期から明治にかけ、西洋文化が急速に入るようになる。
鍵・錠も例外ではなく、洋風建築が建てられることに合わせヨーロッパの錠前が輸入されるようになった。著名な錠前ではイギリスのジェレミア・チャブが発明したレバータンブラー錠、通称「チャブ錠」がある。
レバータンブラー錠は開き戸をもつ西洋建築には欠かせぬ建築金物となった。
これまで職人の手作業でひとつひとつ作られていた日本の錠前は、工業製品として大量に製作されるこうしたヨーロッパの錠前に太刀打ちが出来ず、西洋建築の普及に合わせ文化とともに消えて行った。
明治後期からは西洋建築の幅が広がり、諸官庁、銀行、デパート、病院などの大型建築が増加し、やがて一般住宅にも開き戸が普及、ヨーロッパ風の錠前の需要は高まっていく。
はるか古代、中国より渡った海老錠と同様に、こちらも一部の職人による少数の模倣製作から始まった。大量生産となる輸入品に対抗しうるほどの力はない反面、製作コストが安く、かつての和錠文化から引き継がれた職人たちの器用さを武器に「日本製の新しい鍵」の誕生と流通の模索は続いていった。

ヨーロッパの鍵文化が広がりをみせる中、ある人物が錠に関する特許を申請した。
明治26(1893)年に二上外次郎が申請した「錠(覚眼器附)」である。
この機器は錠を操作するために鍵穴をふさぐフタをずらすと覚眼器といわれるベルが鳴りだす装置が仕込まれている。この錠前の着目すべきところはこの仕組みだけではなく、まだ日本に入って間もないレバータンブラー錠に類似した仕組みをもつ錠前を入れている点だ。その後改良を重ねたものも含めて、これらの仕組みは外次郎が本業である大工仕事に合わせて行っていた時計、自転車、そして錠前の修理のノウハウが育てたアイデアから生み出された発明品であった。柱時計の鐘がなる構造を応用したのか、「自動鳴鐘装置」のゼンマイを巻いておき、条件がそろえばベルが鳴り続ける仕組みとなっている。
しかし「阿波錠」をはじめとした和錠と同様に、少数生産に頼らざるを得ず、民間への広い普及はなかったと言われている。だが、普及はなかったとしても日本における錠前文化のひとつの分岐点ともなったことには変わりはないだろう。
撮影協力:株式会社日本ロックサービス
外次郎の覚眼器附錠の誕生からしばらく経ち、大正3(1914)年には現在のゴールの前身である大阪白玉錠製作所が「白玉錠」という錠前の生産をはじめる。
これが日本における本格的な錠前生産の第1号とも言われている。
「白玉錠」は白磁のノブ(握り玉)と鋳物製の錠本体をもつケースロックである。
ケースロックとは「箱錠」とも呼ばれ、デッドボルトと呼ばれる閂(かんぬき)とラッチボルトと呼ばれる、扉が風などで勝手に開かないように仮に閉めるための部品と開閉機構をセットにした錠前のことを言う。それまでの錠前よりも強度、耐久性が高く、現在でも玄関錠として広く流通している錠前の1種である。
ケースロックの開閉機構には2種あり、日本においては明治前期からレバータンブラー方式(錠)が主流ではあった。
しかし日本では江戸時代であった1848年にはライナス・イェールがピンタンブラー方式のシリンダー錠を発明していたとされている。日本でもこのピンタンブラー方式の錠前が東京・丸の内の大型ビルに採用されるが、それははるか数十年後の昭和まで待たなくてはならない。
当然ながら当時の日本において、その必要性を全く感じなかった訳ではない。
昭和2(1927)年に商工省が蒲田製作所にシリンダー錠の研究開発を委託した記録がある。
またこの委託事業の後、昭和5(1930)年に蒲田製作所の事業を引き継いだ日本金具株式会社(後のニッカナ、NHNの前身)が設立され、蒲田製作所時代に行き詰っていたピンタンブラー方式の錠前開発を成功させた。あるいは別の資料では前年、昭和4(1929)年には堀商店がピンタンブラー方式の錠前製造を始めたと言われている。
日本の企業による錠前の自主生産が活発化するかと思われたが、第二次世界大戦がはじまり金物メーカーは軍需産業へ転向し、冬の時代を迎えることになる。